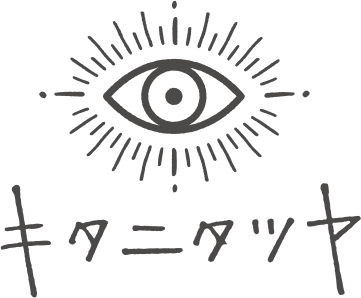葬式は立春の、まだ溶け残った雪がじゃりじゃりと靴裏を濡らす頃だった。
火葬場までの長い坂道は、この年になると随分堪える。
義娘が
「お義父さん、大丈夫です?少し休みましょうか。」
と気遣ってきた。
「いや、先に行ってくれていい。すぐ追いつくよ。」
と返すとしばし逡巡していたが、孫のおかあさーん、という叫び声に振り向き
「じゃあ、待っていますので。」
と言いおいて子供の元へ歩き去っていった。
ころばないようにねー、という声に はあい、という明るい返事が聞こえてくる。
目を細めて彼女らを見送った後、はあと息をついて来た道を振り返った。
ふるさとは今日も曇天に煙っている。
残り雪に包まれて、灰一面の景色の中ただ家屋だけが点々と黒い影を残していた。
この北の街では桜は咲かない。
まだ冷たい、それでも冬の頃と比べれば随分と険のとれた風が頬をなぶった。
背広の内ポケットから、タバコを取り出す。もう体に染みついた動きで一本咥え火をつけると、はあ、と煙を吐き出した。青みがかった煙が風に溶けて消えてゆく。そういえば、もう随分吸っていなかったな、とじんと苦く痺れた脳内で思った。
もう、そんなに吸ったら体に悪いですよ。というあいつの声が心で響いて、
「そんなこと言って、おまえの方が先に逝っちまったじゃないか。」
なんて文句が煙と共に流れていった。
あいつがここに嫁入りしてきた最初の春、一番悲しがったのが桜の見えないことだった。
「もう三月も終わりですよ?だのにまだ雪があるなんて!」
「そういうところなんだから仕方ないだろう。東京とは違うんだよ。」
「それは知ってますけど、桜なんて日本中で咲くものだと思ってました。お花見はどうするの?ひな祭りは?」
「おまえ、もう嫁いできたんだからひな祭りは必要ないだろう。」
「ま!そういうことじゃないんですよ!」
なんて顔を赤くしながらそれでも言い募ろうとするので、
「五月になったら街の方にはちょっとは桜があるらしい。そしたら一緒に観にいこう。」
と宥めると途端に目を輝かせて絶対ですよ、約束ですよと笑ったものだった。
結局五月、街に出て花見をした頃にはもう春というよりは梅雨に近い季節で、桜並木の石畳は雨に濡れていた。
雨宿りをしようというのに、あいつは
「こぬか雨ですよ、風流じゃないですか。」
なんていって平気な顔で雨のなかをすたすた歩いていく。
慌てて追いかけて傘を差しかけても、もうあいつの服は濡れて色を変えていて
「今差したって仕方ないじゃないですか。」
とおかしそうに笑うまつ毛からは雨雫が滴り落ちてこぼれていた。
ほう、と思わず見惚れていると、どうしたんですか、なんて訝しそうに訊く。慌てて何でもない、と誤魔化した。
それから二人で、雨のなかゆっくり桜を見て回った。花見客も少なく閑散とした通りを、薄白の桜を見ながら歩くあいつはどうにも美しく儚く、それでいてとても脆く見えて、ねえ、綺麗ですね、と掛けられた声にああ、綺麗だ、と返すのが精一杯だった。
もう随分前のことだ。
気がつくとタバコの火は消えていて、はたはたと小雨が降り始めていた。
アスファルトの道は瞬く間に滲んで黒くなっていく。これはいけない、と急いで坂道を登り、火葬場に入る。
入り口で渡されたタオルで服を簡単に拭って周りを見てみると、親族はもう全員揃っているようだった。
「それではお別れの儀式となります。」
葬儀屋の声が静かに響いた。
列になった親族たちが、粛々と手向けの品を棺に収めていく。
「最後は喪主様が。」と促されて立ち上がった。死化粧を施されたあいつの顔は通夜で一晩中眺めていたが、これで見納めか、と覚悟を決めながら棺に向かう。
顔を覗き込んで、思わず息を呑んだ。
見事な桜の花が一枝、あいつを包み込むようにして咲いていた。
薄桃の繊細な花びらが柔らかく輪郭を包み、頬は上気したようにまろく紅く色づいて、唇はゆるく弧を描いている。声をかければ今にもあの、春の日差しのような笑い声がまろびでてきそうだった。
「おまえは、 ほんとうに、 綺麗だなあ。」
呟いて、手に持った写真をそっと棺に入れる。褪せたフィルム写真の中の二人は、白無垢と紋付袴を着て照れくさげに、でも幸せそうに笑っていた。
点火を済ませ、控え室で会食をしている時にふと気がついて息子に声をかけた。
「おい、あの桜、誰が入れたやつか知ってるか?」
「桜?」
息子は訝しそうに首を傾げる。
「ほら、棺に入ってたろう、おおきい桜の枝が。というかまずどこで手に入れたんだ?今、二月だぞ。」
息子は不審そうにしていたが思い当たるものがあったのか、ああ、と声を上げた。
「あの花ね。桜じゃないよ。梅、梅。」
「梅?」
「ほら、お父さんがお母さんのために庭に植えたやつ。枝分けしてもらったのがあっただろ?」
そういえば何年か前に庭の梅を分けた覚えがある。あれは桜ではなく梅だったのか、見間違えるとは。葬儀の間は冷静だったつもりだが実は結構動揺していたらしい。
「お母さんあの梅の木随分大事にしてたからさ。逐一世話して、花が咲くたびに嬉しそうに眺めて。だから、一緒に送ってあげたいなって。」
そうか、いい手向けだな。そういうと息子はあいつによく似た顔をそうだろ、とほころばせた。
庭に梅を植えたのは、家を持ってしばらくしないくらいの頃だった。植木屋からもらった梅を、えっちらおっちら運んでいるところを見たあいつは目を丸くしていた。
「なんですそれは?」
「梅だ。せっかく広い庭があるんだから使わないと勿体無いだろう。」
「まあ立派な枝!これは実のなるやつですか?」
「花梅だが実はつくことにはつく。が、食べるのには向かないな。種が大きいし、美味しくないそうだ。」
「あら残念。でも綺麗なんでしょうね。」
上機嫌のあいつは、何か手伝いましょうかと言ってくる。いや、いい。と返しながらシャベルを手に穴を掘り始めた。
「おまえ、春に桜が見れないと言っていたろう。」
「ええ、言いましたけど、それが?」
不思議そうな声を背中で聞きながら、シャベルにぐっと力を込めた。
「梅なら三月には咲くからな。豊後といって、桜に似ている品種だそうだ。桜じゃあないが、これで風情くらいは味わえるだろう。」
照れ臭さで熱くなっていく頬をあいつには向けられず、穴掘りに精を出しているふりをする。
土塊をわざと乱暴に横に放ったところで、静まり返った背後に不安になって
「や、やっぱり桜じゃないと嫌だったか、梅は嫌いか。もし嫌いなら返してこられるが、」
と振り返ると、いきなり柔らかいものが体にぶつかった。
慌てて抱き止めるとあいつは腕を目一杯に回してぎゅうぎゅうと抱きしめてくる。困惑しながら抱きしめ返すと ぱ、と顔をあげて
「好きです、とても嬉しいです、大好きです。ありがとうございます。」
と満開の笑みで言った。
「あ、ああ。」
頬を真っ赤にして答えると、あいつも頬を赤くしてふふ、とはにかんだ。
これで家から花見ができますね、楽しみですね、と笑うあいつにそうだな、と答えて、それから家の庭にはずっと梅の木が植わっている。
あいつは甲斐甲斐しく梅の木の世話を焼いていた。剪定は植木屋に頼んだが、肥料だの虫の駆除だのを熱心に調べていて、植木屋より詳しいこともあるほどだった。
容体が悪くなって入院することになった時も、挿し木した鉢植えを持っていきたいと言っていた。
根付きのものは縁起が悪いから駄目だ、と言っても頑固なもので、結局鉢植えは毎日面会の時に持っていくことになった。
水仕事でいたんだ桃色の指先が薄い花弁に優しく触れる時、あいつは眩しいほど穏やかな顔をした。今日の出来事をぽつぽつと話して、それに時折相槌を打つ。カーテンで遮られた柔らかい日光の入る病室で、その時だけは病気も、体の心配も忘れていられたものだ。
「拾骨のお時間です。」
葬儀屋の言葉で我にかえる。台の上の灰色の骨たちはやたらと現実味がなくて、これがあいつだというのはどうも信じられなかった。最後、小さい喉仏の骨をころん、と骨壺に収めたらおしまい。抱えた箱は思っていたより随分軽い。
「おまえ、小さくなっちまったなあ。」
と独り言が口を吐いて出た。
最後にあいつを抱えたのはいつだっただろうか。
そういえばいつだかの春、東京に花見をしに行ったことがあった。花便りをテレビで見ては、ここに桜前線が来るのはいつ頃かしらねとはしゃぐあいつに
「こっちから会いに行ってもいいんだぞ。」
というときょとんとしていた。
「桜前線だ。別におとなしく待つことはない。こっちが南下して見に行けばいい。」
「何言ってるんですか、仕事があるでしょう。」
「今度東京に出張の用があるんだが、二日目には用事は済むんだ。」
嘘だった。出張があるのは本当だが、休暇は別に確保してある。
滅多にとらない休みをとって、柄でもない誘い文句を吐いているのは、結婚して二十年目の記念日が近いからだ。節目を気にするような初々しい間柄ではもうないにしても、何かしたいと思ってしまったのだ。
「その、だからどうだ、たまにはゆっくり観光でも。」
言い切って顔を上げると、あいつが何やらにやにやしてこちらを観ていた。
「なんだその顔は。」
と訊いても
「いーえ、なんでもありませんよ。」
と言いながら余計ににやける。
恥ずかしくなって
「嫌ならいいんだ、行かなくたって。」
とぶっきらぼうに言い捨てると
「あら、行かないだなんて言ってないじゃないですか。いいですね、東京のお花見。もう何年も帰っていないもの、楽しみだわ。」
なんていうのだからそっと安堵の息を吐いたりしたものだ。
東京での会合を終えてホテルに帰ると、あいつはもうすっかり着替えて入り口前で待っていた。外に立っていたものだから春だとはいえ随分冷えただろう。
慌てて中に入って、まだ用意があるのだから部屋で待っていてくれてよかったのにと言うと、あなたを出迎えたかったのだと笑った。
愛おしさに思わず手を伸ばすと、艶やかな髪はしんと冷えてそこだけ冬の残香までするようだ。そんなに長く待っていたのか、と驚いてすぐ支度する、ちゃんとお前も暖かくしていけと云い聞かせては着替えに急いだ。
テレビの予報通り、桜はちょうど満開を迎えた頃だった。さすがは東京というべきか、有名な桜並木のある通りは人で賑わっている。
立ち並ぶ屋台を見ながら、二人で桜の舞い散る歩道を進んだ。
折しも強い風が吹き、桜吹雪が視界を覆う。
目の前が薄桃に霞んだその隙に、あいつの肩に乗っていたショールが飛ばされる。ふわ、と風に乗った若草色は、幸運にも桜並木のそれほど高くない枝に絡め取られた。
「あらあら大変。」
急いで駆け寄って手を伸ばしているが、いかんせんあとちょっとで届かない。
ひらひらと舞う桃花色の小さな手が悪戯心を誘って、近寄ってひょいと後ろから抱え上げてやった。
ひゃあと素っ頓狂な悲鳴が上がるのに笑みを堪えながら、
「ほらこれで届くだろう。」
と言えば
「届きます、届きましたからおろしてください!」
と慌てた声が降ってきた。
くすくす笑いながらおろしてやると
「もうこんな恥ずかしいことったらないわ!子供みたいに持ち上げられて。あなたももう若くないんですから無理しないでください!」
なんてつむじを曲げている。
「軽かったから大丈夫だぞ。」
と笑うとそういう問題じゃないんです、だいたいこんなに人のいるところで、とそっぽを向いてしまった。
悪かったよ、と謝るとようやくこっちを見て、途端にふふ、と吹き出した。
どうした、何がおかしいと困惑しているとこっちに手を伸ばして、
「桜がついていますよ。」
と髪から花びらを摘み取った。もう本当に子供みたい、と笑うあいつの髪にも桜の花弁がくっついていて、思わず二人で笑い合ったものだ。
しばらく桜並木を堪能したが、流石に人ごみに疲れてきたので早々に退散して、少し外れの茶屋の店先で一息つくことにした。
くしゅん、とくしゃみの音が隣でする。
花冷えですかね、なんて呑気な声に ホテルの外で待っていたからだろう、とは思うが口には出さず、湯呑みの茶をずず、と啜る。
「いい天気ですねえ」
「そうだな」
「ねえあなた。」
改まった声色にどうしたことかと横を見ればあいつはまっすぐこちらを見ていた。
「二十年前、私と結婚してくれてありがとうございました。」
「おぼえていたのか。」と驚いて訊くと
「もちろん、記念日ですもの。あなたが手帳に印をつけていたのも見ましたよ。」
ホテルも調べた跡が机に置いてありましたし、出張にかこつけていろいろ準備してくれていたんでしょう、ありがとうございます。とあいつがいう。
計画が筒抜けだったことを知り、恥ずかしさで顔がかあと熱くなった。
「出会ってくれて、ありがとうございます。」
「これからも、ずうっと一緒に春を迎えましょうね。」
こちらこそよろしく頼む、と返すとええ、と頷く。柔らかい笑みを浮かべたあいつは、本当にいい天気ですねえ、とまた花を見やった。
春の長閑な昼下がりは時間の流れが眠くなるほど緩やかで、花見客のさざめきもここでは心地よく耳をくすぐるほど遠い。桜が時折風に揺れて、そのたび花びらはさらさらと薄桜の軌跡を描いて滑り落ちていった。ゆっくりと茶を飲みながら、心地よい空気に身を任せる。
「また来たいな。」
「今度来るときはいつになるかしら、もうおじいちゃんおばあちゃんかもしれないわね。」
「そんなに遠くはないさ、それに今だってそんな若いわけじゃないだろう。」
「ま!失礼だわ」
拗ねた顔を思い出す。また戻ってこよう、と思いながらなんとなく機会が巡って来ず、結局東京での花見はあの一度きりになった。きっかけなどなくても、連れていけばよかったと今悔やんでも仕方ないのだけれど。
あの時桜の下で抱き上げた、柔くて重量のある温もりを思い出す。
今は似ても似つかぬ白い骨箱は、ただただ拍子抜けするような軽さと無機質な温度を伝えてくるだけだった。
火葬場を出ると雨はもう止みそうで、はたはたと降る雫の合間からは日光が差してきていた。
しぶとく道路の脇にしがみついていた残雪は雨で大分溶けてぬかるんだようだった。
「ゆきげ雨ね。」
と誰かの声がした。
雪解雨。冬に降った雪を溶かす春の暖かい雨。
細い柔い糸のように肌を濡らす雫たちは、折しも差した日に反射して光の束のように見えた。
雲間から逃げ出した光たちが天使の梯子を作っている。
何かが緩んで、ため息が口から抜けていった。肩からふっと力が抜ける。老眼のせいか、景色を見ようとしてもどんどん滲んでいって輪郭がぼやける。思わず目を擦った。
濡れた頬を、風がゆるく撫でていく。角の取れた、ぬるい春風だ。
春が来るな、と思う。あいつの好きだった季節だ。
あいつの好きな季節は、あいつがいなくても巡ってくる。そんなことがどうも不思議に思えて、これからあいつなしで過ごす時間が途方もなく長く感じた。
それでも春はやってくる。
これから、何度だってやってくる。
口が、あいつの名前をかたどった。
ふと、何十年も前のことを思い出した。
可愛らしく着飾った娘姿のあいつに、花見に行こうと持ちかけたのは春真っ盛りのことだった。
賑わう大通りから少し外れたところ、見事な枝垂れ桜の下で花を見上げるあいつはとても綺麗だった。
ひらひらと舞う花弁を指で追いかけている横顔に、一世一代の勇気を振り絞って声をかける。
「ちはるさん。嫁に来てくれませんか。あなたと、これから何度も春を過ごしたい。二人で一緒に。千でも、二千でも。」
ちはるは、花のような笑顔ではい、と答えた。