|
「ジェイミーをただのドラムン・ベース・プロデューサーとして断言するのは難しい。夢想的なトリップ・ホップやアムビエントから、ハウス・リミックスやシンフォニックなブレイク・ビーツまで、彼の音楽性の幅広さには目を見張るものがある」(URB誌) |
|
はじめて彼の音楽を聴いた時、このURB誌による賞賛の言葉が一番ぴったりくると思った。本作の主人公ジェイミー・マイヤーソンは、ドラムン・ベースという世界だけで語るにはどうかと思うぐらい、とにかく幅広い音楽スタイル/
引き出しを持ち合わせているアーティストなのだ。ドラムン・ベースにしても、トリップ・ホップにしても、ハウス、アムビエント…それらが単なる一つの枠で表現されることなく、すべてにおいて何らかの特徴的な要素と融合して素晴らしく調和している点でも評価すべき人なのである。にもかかわらず、の一方英米各音楽メディア等ではこうした賞賛もある。「最もすばらしいアメリカのジャングリスト」(メロディ・メーカー誌)「ついにアメリカ人ドラムン・ベース・アーティストの登場!」(ID誌)「ジェイミーは今後目が離せないアーティストだ」(Keybord
Magagine) |
|
つまりジェイミー・マイヤーソンがドラムン・ベースというジャンルを中心に注目されている一要因に、彼が“アメリカから登場したミュージジャン”だということだということが大きい。そして今回、ジェイミー・マイヤーソンのファースト・アルバムの内容に関して各誌がさまざまな言葉で絶賛している中、ドラムン・ベース云々にとらわれないで、もしろ私はこういった評価もより多くの人に伝えたいと思う。「アグレッシヴなドラムン・ベースよりも、メロディックな曲でほっとしたい人にぴったりなアルバム」(Alternative
press 誌) |
|
---そう。テクノというフィールド、ダンス・ミュージックというイメージから飛び出して、一般的なポップスを聴いている人々にも充分アプローチ出来る音楽なのだ。 |
|
ちなみに最近いろんな方面で耳にする“ドラムン・ベース”というのは何であるか。そもそもそれは、90年代イギリスのアンダー・グラウンドなダンス・シーンから起こったブレイク・ビーツ・ミュージックから派生した新しい音楽フォーマット。当初はそのちょっと速めのブレイク・ビーツとダビーな感じのベース音がジャングルといわれるものとなり、そうした形態からBPMをより速め、ある種バップ・ジャズ的な要素も感じさせる技巧やコラージュ感覚によって発展したのもの等がドラムン・ベースといわれるが、それ自体も既に常に現在進行形で進化し、いろんな形で広がりつつあるジャンルの音楽用語だ。“ドラムン・ベース”とはイギリスが生み出したものであり、4ヒーロー、ゴールディ、LTJブケムといった御大、そしてスクエアプッシャー、フォーテックといったアグレッシヴで斬新性のあるものなど、その他いろんなミュージシャンが活動している。 |
|
つい先頃ニューヨークから得た情報なのだが、当地ではテクノ、ヒップホップ、ハウスなどがメイン・ストリームだったが、最近大型クラブにロンドンからドラムン・ベースの人気DJらがやってくるようになり、ようやくドラムンベースとジャングルがクラブでのシーンが確立されてきたそうだ。ニューヨークの月刊情報誌『Paper』の97年アニュアル・レポートでも、クラブではジャングル〜ドラムン・ベースが目立った年だったとレポートされていた。世界の最先端情報に敏感な日本のリスナーにはちょっと信じられない話だが、このジェイミー・マイヤーソンがなぜこれ程までにアメリカ初のジャングル〜ドラムン・ベース・アーティストなどといわれ、メディアを中心としてその活動が注目されているのは、そうした背景もある。実際、ジェイミー・マイヤーソン自身は自らの音楽をドラムン・ベースではなく、単なるエレクトロニック・ミュージックと断言していることも事実であり、それは彼のアルバムを聴いてもらえれば一目瞭然の事実だ。 |
|
さて、ここでジェイミー・マイヤーソンの経歴を紹介していこう。 |
 ジェイミー・マイヤーソンはニュージャージー州出身の現在22歳の青年。ものごころついた時から既に音楽関係の仕事に就きたいという夢を抱く少年であり、まず彼が興味を示したのはドラムスとパーカッションであった。13か14歳の頃である。そんな彼が好んで聞いていた音楽は、両親の影響からビリー・ジョエルやジェイムス・テイラーといったAOR系やジャズ・クラシックのもの、そしてザ・キュアー、デペッシュ・モード、ニュー・オーダー、ザ・スミスといったブリティシュものも好きで、彼の音楽的バック・ボーンにポップ・ミュージックへの傾倒が大きく挙げられる。中でも彼が音楽をやるきっかけとなったのはデペッシュ・モードだという。 ジェイミー・マイヤーソンはニュージャージー州出身の現在22歳の青年。ものごころついた時から既に音楽関係の仕事に就きたいという夢を抱く少年であり、まず彼が興味を示したのはドラムスとパーカッションであった。13か14歳の頃である。そんな彼が好んで聞いていた音楽は、両親の影響からビリー・ジョエルやジェイムス・テイラーといったAOR系やジャズ・クラシックのもの、そしてザ・キュアー、デペッシュ・モード、ニュー・オーダー、ザ・スミスといったブリティシュものも好きで、彼の音楽的バック・ボーンにポップ・ミュージックへの傾倒が大きく挙げられる。中でも彼が音楽をやるきっかけとなったのはデペッシュ・モードだという。 |
|
マイヤーソンは当時、いろんなバンドに入るなどして音楽活動にチャレンジしていたが、結局自分のやりたいことを理解してくれるバンドに巡り合わなかったことから、一人でもできるエレクトロニック・ミュージックの世界へ入っていった。 |
|
91年頃からマイヤーソンは自分の部屋に簡単なスタジオを作った。そしてピアノを始め、新しいキーボードの音作りに没頭し、メロディク、ピプノティック、エレクトロニック、ドラムン・ベース、ブレイク・ビーツ、ハウス等のダンス・ミュージックなどをコンピューターを駆使して様々なスタイルのサンプルを作る。そこには当時影響を受けていた808ステイトや、マイヤーソンが今まで培ってきたドラムのセンスを活かした、他のテクノ・アーティストの追従を許さないプログラミングやオリジナリティを生み出してきた。 |
|
93年9月、当時18歳のマイヤーソンはフィラデルティア州にある611レコードへ出向き、ディゴと出会う。ディゴはイギリスのユニット、4ヒーローのメンバーであり、ジャングル〜ドラムン・ベースに関してはパイオニア的なレーベル、レインフォースト・レコードの経営者であることは皆さんもご存知であろう。がしかし、マイヤーソンはディゴがどんな人物か知らず、とりあえず渡したデモ・テープがきっかけにレインフォースト・レコードとの関係が始まったのだ。ディゴは自分たちが主宰する『ENFORCER
VOLUME 6 & 7 COMPILATION』にマイヤーソンの楽曲を収録した。 |
|
当時のマイヤーソンはコネチカット州のハートフォード大学で音楽経済学を学びながら、夜はレインフォースト・レコードのミュージシャンとしてドラムン・ベースのレコーディングををするという生活を送っていたが、そんな活動が徐々に多方面で注目されるようになる。 |
|
94年、レインフォースト・レコードから9曲入りの「Matter Of Trust」を、そしてニューヨークのSm:)e・コミューニケーションから3曲入りの「Lonly
World」をリリース。彼はアメリカにおけるドラムン・ベース・シーンの先駆者として評されるようになり、現地のファンを魅了し、各音楽誌も彼の音楽性を絶賛し始めた。その他の彼の作品として、イギリスで定期的にリリースされているブックレット付オムニバスCDのテクノ編『TRANCE
ATLANTIC vol.2』(このシリーズの日本アーティスト盤が「Pacific State」に当たる)や、コンピレーション『Jungle
- The Sound Of The Underground』にも参加している。また、リミキサーとしての活動としてダブスター、ラガ
& ザ・ジャック・マジック・オーケストラ、シェオフリー・ウィリアムスなどを手掛けている。 |
 結局、ジェイミー・マイヤーソンはベルギーのクラムド・ディスクやSm:)e・コミューニケーションを経て、フィラデルフィアのコロムビア傘下のオーヴァム・レコードと契約し、今回の正式なファースト・アルバム『ザ・リッスン・プロジェクト』をリースするまでに至ったのである。 結局、ジェイミー・マイヤーソンはベルギーのクラムド・ディスクやSm:)e・コミューニケーションを経て、フィラデルフィアのコロムビア傘下のオーヴァム・レコードと契約し、今回の正式なファースト・アルバム『ザ・リッスン・プロジェクト』をリースするまでに至ったのである。 |
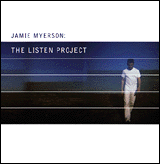 この『ザ・リッスン・プロジェクト』は冒頭で述べたように、単なるドラムン・ベースのアルバムではない。マイヤーソン曰く、「レスキュー・ミー」と「ディス・タイム」は“自分の原点”という意味で重要な曲だという。前者はキャロル・トリップという女性ヴォーカルをフィーチャーした親しみやすいハウス的なナンバーだ。そして後者はまるでデペッシュ・モードを彷彿とさせるようなエレクトロニック・ポップが基盤になっている。「僕がエレクトロニックの世界にいる限りは、伝統的な要素の中にエレクトロニックなものをミックスし続けるだろう。自分自身同じ事を繰り返すのには納得しない」 この『ザ・リッスン・プロジェクト』は冒頭で述べたように、単なるドラムン・ベースのアルバムではない。マイヤーソン曰く、「レスキュー・ミー」と「ディス・タイム」は“自分の原点”という意味で重要な曲だという。前者はキャロル・トリップという女性ヴォーカルをフィーチャーした親しみやすいハウス的なナンバーだ。そして後者はまるでデペッシュ・モードを彷彿とさせるようなエレクトロニック・ポップが基盤になっている。「僕がエレクトロニックの世界にいる限りは、伝統的な要素の中にエレクトロニックなものをミックスし続けるだろう。自分自身同じ事を繰り返すのには納得しない」 |
|
そうした姿勢が貫かれたエレクトロニック・ミュージック・アルバム。オープニングはスタイリッシユなジャングル、そして夢想的なトリップ・ホップ、アムビエント、シンフォニックなブレイク・ビーツ、女性ヴオーカルとドラムン・ベース・サウンドとの調和など、実に幅広いエレクトロニック・サウンドの要素が詰まっているものだ。そして、皆が注目する彼のドラムン・ベースだが、その手法はいろんな形で表現されていて、中でもメロディックなポップと融合したものが特徴的である。それは、彼の基本形には音楽の世界に進もうとしていた時によく聴いていた数多くのポップ・サウンドからの影響というものがあるからなのだろう。 |

「大それたことをやろうとか、セールス的な成功を望んでいるわけでもないし、雑誌表紙を飾るようなスターダムにのし上がろうという野望もない。僕は、ただよい音楽を創りたい。そしてみんなが楽しんでもらいたいだけなんだ」 |
|
ジェイミー・マイヤーソンは本当に純粋なエレクトロニック・ミュージック愛好家であり、またクリエーターとしても素晴らしい感性をもっている。それらが今後どんな形に成長していくのかとても興味深い。このアルバムを聴いてもらえれば、その期待が膨らむにちがいないと確信している。 |
|
98年3月 高村立子 (SPECIAL THANX K.D. & CROMHEARTS) |
1998 (C) Sony Music Entertainment (Japan) Inc.
|